第六話 牙城クスコ(5)
翌朝――クスコ戦当日の朝――インカ軍の総指揮官トゥパク・アマルは、進軍準備を整えた全軍の前にその姿を現わした。
戦時には常のごとく、かつてのインカ皇帝が戦闘服として愛用したのと同じ金糸の入った黒ビロードのマントに、分厚い皮製の甲冑を付け、その胸には黄金の太陽を象(かたど)った首飾りが輝く。
そして、その腰には重厚なサーベルと、厳(いか)つい銃が備えられている。
爽やかな夏空は真青な蒼穹を描き、風に舞うトゥパク・アマルの漆黒の長髪を、優雅に美しく浮き立たせていた。

彼は白馬に跨ったまま全軍の正面に進み来ると、あの包み込むような、それでいて激情を秘めた切れ長の目で、一人一人の兵たちを隅々まで見渡した。
それから、手に持っていた、かのインカ皇帝の象徴、金の笏杖を、その逞しい褐色の腕で真っ直ぐに天頂指して掲げ上げた。
その瞬間、天空と大地の気と光が、その笏杖に吸い寄せられるがごとくに笏杖を包み、今、笏杖は、まるで黄金色の炎を纏っているかのように見える。
全軍の兵たちは思わず固唾を呑み、どこか酔いしれたような眼差しになっている。
そんな彼らが見守る中、まるでその笏杖の気と光とが波動となって流れ込んでいくがごとくに、トゥパク・アマルの全身も黄金色の炎に包まれる。
夢か現(うつつ)かさえ定かでなくなるようなその光景に、兵たちが、そして、彼の側近たちもが、恍惚の表情で息を詰めた。
トゥパク・アマルは、深遠な、しかし、はっきりとした声で話しはじめた。
「皆の者よ!!
今日、この瞬間まで、本当によく戦ってくれた!!
インカの神々も、そなたたちの奮戦を深く讃(たた)えているに相違ない。
わたしが、神々に代わって、今、そなたたちに深く礼を伝えたい」
そう言って言葉を切ると、トゥパク・アマルは笏杖をガッシリと掲げ持ったまま、本当に兵たちの前に頭を下げた。
恍惚と驚きの気が兵たちの間に漲り、その次の瞬間には、兵たちも、また、トゥパク・アマルに向かって深々と頭を下げていた。
トゥパク・アマルは、そのような兵たちに、いっそう深く包み込むような眼差しを向けながら、彼自身も込み上げるものを胸におさめるがごとくに、ゆっくりと、深く頷いた。
そして、真に真摯な声で続ける。
「わたしは、そなたたちの誰一人の命とて、決して失いたくはない。
インカの神々の加護が、そなたたち一人一人にあらんことを!!」
トゥパク・アマルは、再び、真っ直ぐ、天空に向けて黄金の笏杖を翳(かざ)し上げた。
朝の煌く陽光を反射して、笏杖が眩い閃光を放つ。
「この笏杖は、かつては、インカ皇帝の権威の象徴であった。
だが、今は違う!!
これは、そなたたち、一人一人のもの!!
もはや、このインカの地に支配者はいらぬ。
そなたたち、一人一人が、皆、等しく、この大地の主となるのだ。
自由と幸福をつかみ、他者を愛し、支え、真に己(おのれ)自身として生きよ!!
そのために、我らを支配する侵略者たちの枷(かせ)を、今こそ断ち切ろうぞ!!」
トゥパク・アマルは、さらに天空高く笏杖を持ち上げた。
「忘れるな!!
この笏杖は、そなたたち、一人一人のもの!!
今こそ、インカの地を、我らインカの民の手に!!」
そして、その美しく精悍な横顔を、真正面から兵たちに向けた。
彼の漆黒の長髪と黒いマントが、翼のごとくに風に舞う。
そのまま、彼は蒼く燃え立つような瞳で全軍を見渡した。
その全身からは黄金色のオーラが煌々と放たれる。
「いざ、進軍ぞ!!」
その瞬間、大地を揺るがすほどの激しい士気が全軍から漲った。
「オーッ!!」
トゥパク・アマルの鼓舞に呼応して雄叫びを上げるインカ軍全体から、強い熱気が渦のように立ち上り、巨大な波となってうねり、高まっていく。
かくして、運命のクスコ戦は、今、ついにその火蓋が切って落とされたのだった。

一方、同じ頃、クスコの市街地では、かのモスコーソ司祭がスペイン軍に大演説をぶっていた。
日の出と共に、モスコーソは、中央広場にスペイン兵及びクスコに在住する民衆たちを総結集させた。
彼は広場中央に設置された壇上に姿を現したかと思いきや、なんと、その司祭の証とも言える裾長の僧衣を、突如かなぐり捨てたのだった。
兵も、民衆も、驚愕と興奮の眼で、喰い入るように司祭を見上げる。
さらに、モスコーソはその手に武器を取って逞しい馬にうち跨り、軍人のごとくの厳しい風貌で、民衆の面前に威風堂々たる物腰で進み出た。
そして、太く、響く声で、天にも届くがごとくの大いなる迫力で、叫ぶように言い放った。
「スペイン王陛下の忠実なる臣民たちよ!!
この国の平穏と秩序を取り戻すために、そして、尊きカトリック教会を悪魔どもの手から守り抜くために、かの謀反人トゥパク・アマル率いる反乱軍を徹底的に撃退せよ!!」
そのモスコーソのいかにも華々しいデモンストレーションは、さすがにスペイン軍の士気を大いに高めた。
それが合図となり、クスコの軍勢たちは、インカ軍が陣を張るピチュ山目指して一斉に突撃を開始した。
スペイン側に比して著しく火器の武装に劣るインカ軍は、トゥパク・アマルを中心に、この日のために対抗策を懸命に模索してきた。
いかに敵の銃弾を逃れながら有利に戦いを展開させるのか、そのことを考え続けてきた結果は、自然な帰結として、防御優勢の態勢をとる戦略につながっていた。
戦場では、銃剣突撃する攻撃部隊よりも、待ち受ける守備部隊の方が有利である場合が少なくない。
特に、火器の使用される戦場では、一般的にも、圧倒的に防御側が有利になるのである。
単純に考えても、敵の銃弾の命中率は全身の何パーセントを暴露しているかで全く異なってくるのであり、実際、防御側が塹壕から頭だけ出して敵を撃つのと、攻撃側が全身を晒して撃ちながら進んでくるのとでは10倍近くも命中率が違ってくる。
つまりは、それがそのまま攻撃側の死傷者数増大へと直結するわけである。
特に、クスコのスペイン兵たちは、この数日間、インカ軍にピチュ山という有利な地勢を占拠されて以来、非常なプレッシャーを受けながら恐慌状態にあった。
そうした激しい抑圧感が、今、戦闘の開始により一挙に解放され、それは闘争心を非常に高めていた一方で、本来の抑制をききにくくするという、危うい状態をも引き起こしていた。
歴史上の記録によれば…――とは言えども、多くの記録はスペイン側の手により残されたものであるから、スペイン側にかなり有利に書かれていることを念頭に置く必要があるが――このクスコ戦では、それこそ若く果敢なスペイン兵たちは、十分な弾薬をもってインカ軍めがけて肉弾突撃を敢行しようとするのを、上官から止められて、やっとこらえたほどであった――というから、その士気は相当に高かったと考えられる。
だが、その分、スペイン側は攻撃に意気込みすぎていた。
対する、インカ側は、逆に防御が固かった。
一般に、敵を堅固な防御陣地から引き出して攻撃することが、敵の防御率を落とす最善の策である。
今回の場合、スペイン兵たちは自ら勇んで陣営を離れ、反乱軍の陣営たるピチュ山の斜面へと乗り込んできた。
まさに、銃剣突撃する攻撃部隊たる討伐軍を待ち受ける、有利な守備部隊としてのインカ軍という構図であった。
なお、こうした戦場で敵の銃弾を防ぐためには土嚢を積むか塹壕を掘るかして作った防御施設を利用するしかなく、当然ながら待ち受けるインカ軍は既に多くの土塁を積み、また、多数の塹壕を掘っていた。
一方、攻撃してくる討伐軍、つまりはスペイン側は、全身を晒して進んでくるしかなく、既に銃器をも携えているインカ軍と対峙すれば、全身を晒している割合の高い方が当然ながら弾の命中率も高い。
対するインカ軍は、塹壕から頭だけ出して敵を打ち、また、土嚢を三角に積んで中央部から銃身を出して射撃した。
また、これまでの戦果として銃のみならず、数砲の大砲をも奪取していたインカ軍は、ピチュ山の斜面にそれらを配備し、砲弾による攻撃も行った。
インカ軍の砲撃を担当していたのは、その操作を知る捕虜とされた元スペイン軍の兵たちであったため、インカ兵の監視の目をかすめ、敢えてスペイン兵のいないところに打ち込むという裏切り行為もあった。
しかしながら、インカ兵の監視さえ届けば、トゥパク・アマルの指示通りの砲撃が着実に行われた。
大砲の数は討伐隊に比して少ないとはいえ、高所からの攻撃が可能であったことは彼らを有利に導いた。
当然ながら、スペイン軍も大砲による攻撃を絶え間なく繰り返し、砲弾が打ち込まれる度に、インカ兵の群集の中に無情な空隙を空けた。
しかし、それはすぐさま別のインカ兵たちによって埋められる。
このクスコ戦に備え、トゥパク・アマルは事前に南部地域を転戦し、当本隊の総兵力をほぼ4万人の規模に増大させていた。
撃っても撃っても、まるで蘇るように湧き出してくるインカ軍の兵力の無尽蔵なさまに、スペイン軍は次第に恐怖の念を抱きはじめる。
さらには、インカ兵が打ち鳴らし、奏でる、あの大地を揺るがす太鼓の音と天空に響き渡る角笛の音が、常のごとくにインカ軍を鼓舞しながら、彼らを庇護するように戦場の空気を包み込んでいく。
かくしてクスコの強靭なスペイン軍を相手にしてさえも、インカ軍は見事に有利な戦況を展開していったのだった。

トゥパク・アマルの側近たちも、彼らの兵をよく統率して討伐軍の進撃を堅固に防いでいた。
トゥパク・アマル自身は戦場の全貌を見渡せる高台の位置に立ち、インカの神々に守護された、まさにインカ皇帝のごとくの雄々しく気高い光を放ちながら、その鮮やかな采配によって、縦横無尽に全軍の指揮を執っている。
そして、このクスコ戦でも、アンドレスは最前線に立っていた。
聖剣のごとくに蒼く輝くサーベルを振り翳(かざ)し、光のような速さと、恩師アパサに叩き込まれた一縷の無駄もない合理的な身のこなしで、急な斜面を騎馬のまま駆け下りながら敵を次々と薙(な)ぎ倒していく。
無数の銃弾が飛び交うにもかかわらず、まるで弾が彼を避けているがごとくに、それは彼の心眼によって、殆ど意識を超えたところで反射的にかわされた。
彼は敢えて銃器を構える兵の中へ馬ごと乗り込むと、間髪入れず、サーベルを右から左へと一直線に払うがごとくに走らせる。
サーベルの蒼い軌跡が、水平な光の筋を放った。
その蒼い残光を、瞬く間に、敵の腕から噴出した血飛沫が赤く染め上げる。
一方、その激しい動作とは対照的に、アンドレスの美しい横顔は、まるで血を浴びた氷の彫像のように、ぴくりとも動かなかった。
アンドレスはそのまま疾風のごとくに馬を駆りながら、銃器を握る敵兵の腕を狙って切りつける。
まだ無傷のスペイン兵たちが、騎上のアンドレスを狙わんとした瞬間、彼は俊敏に身を翻し、馬から地に舞い降りた。
そして、今度は、銃器を手にした敵兵の中にその身を紛れこます。
味方を誤って討てぬスペイン兵たちが銃を手に躊躇(ためら)うその瞬時の隙に、彼は己の足で疾走し、重厚なそのサーベルを軽々と水平に走らせた。
サーベルが蒼い弧を描いて光の軌跡を残した次の瞬間には、十数名のスペイン兵たちが、その腕、あるいは喉元を確実に切り裂かれ、崩れるように地に伏した。
真紅の血飛沫が、周囲に飛び散り、大地を染める。
兵たちが地に沈むのとは対照的に、アンドレスの姿は上空射して跳躍する。
まるで、宙空に静止するがごとくに、空(くう)で一瞬その身を留め、次なる敵に確実に狙いを定めて敵集団の中に真っ直ぐ舞い降りる。
そして、恐ろしく切れ味の良いその刃(やいば)は、上から下へと敵兵たちの白い肉体をザックリ切り裂いた。
もはや敵を討つことのみに完全に己を投じているアンドレスではあったが、己の手にあるサーベルは、まるで、それそのものが意志を持っているがごとくに、己の意識を超えて、勝手自在に動いているような不気味さを抱かせる。
それは己自身とサーベルとの真に一体化した帰結なのか、あるいは、今やサーベルが己の主(あるじ)となってしまったのか、もはやアンドレスには判断がつかなかった。
だが、そのようなことは、もうどうでもよかった。
敵を斬れればそれでよい!!…――アンドレスは、無我夢中で斬り続けた。
全身返り血に染まり、全く殺人鬼のごとくの不気味な気を放ちはじめた彼の殺気だった形相に、思わず敵兵は怯(ひる)み、後退(あとずさ)る。
そのような敵の一縷の虚を、アンドレスの剣先は完璧に捉える。
次の瞬間には、彼のサーベルが蒼い軌跡と共に、確実に、敵の急所を貫いた。
そして、再び噴出する真紅の血飛沫。
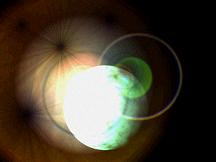
アンドレスの顔は、能面のように表情が無い。
インカのために、もはや己が毒を呑もうが構わない!!
たとえ、己の魂が地獄に落ちようとも、インカの民に真の平和と秩序が戻るのならば…――!!
今、その目と全身からは、赤黒い殺気を覆うように、蒼い焔が煌々と燃え上がる。
一方、味方の将たるアンドレスのその壮絶な姿に、インカ兵たちは圧倒されつつも、強く鼓舞され、士気は激しく高まった。
そして、そのようなアンドレスの姿を、全軍の指揮を執るトゥパク・アマルも、また、高台から見下ろしていた。
トゥパク・アマルは悲愴と情熱を帯びたその目を細め、僅かに頷く。
こうして、クスコでの戦いは絶えることなく、二日間続いた。
かくして、次第に、インカ軍はスペイン軍を圧倒していった。
スペイン側に、目立って焦りの色が滲みはじめる。
その気配に乗じて、インカ軍はいっそう勢いづいた。
望まぬ戦いではあったが、もはや覚悟を決めて着実に敵を打ち崩してゆくトゥパク・アマル…――しかしながら、戦闘開始から三日目の午後、彼の目の中に、突如、その目を疑うような信じられぬ光景が飛び込んできた。
ピチュ山の高台に立つ彼は、首府リマからクスコに通じる長大な街道が遥かに見渡せる。
今、その街道を、クスコ指して勢いよく進軍してくる巨大な軍団の姿があった。
それは、首府リマから駆けつけたスペイン側の援軍――トゥパク・アマルは知る由もないが、まさしく宿敵アレッチェ率いる援軍本隊――であった。
この時、トゥパク・アマルが目を見張ったのは、援軍の大軍が押し寄せてきたことに対してではなかった。
今やトゥパク・アマルの軍勢は、総勢4万を超える規模である。
今更、敵の軍団の数に驚愕するほどのことはなかった。
彼が息を呑んだのは、今、街道を進軍してくるその討伐軍側の援軍の中に、無数の褐色兵たちが混ざっていたことであった!
つまり、トゥパク・アマルたちと同族であるインカ族の者たちが、なんと、リマからのスペイン側の援軍の中に組み込まれていたのである…――!!
しかも、その数、ざっと見渡した印象でも、1万人に達する甚大な規模であった。
さすがに驚愕した目の色で眼下を見下ろしているトゥパク・アマルのただならぬ様子に気付いた護衛のビルカパサが、素早くトゥパク・アマルの視線を追う。
その視線の先に見たその敵方の褐色兵の軍団に、ビルカパサもまた、息を呑んだ。
――リマの褐色兵――それは、アレッチェの策謀により討伐軍に組み込まれた、トゥパク・アマルの軍団必殺の秘密兵器でもあった。
アレッチェはクスコに到着するやいなや、クスコの討伐軍がインカ軍に圧倒されているさまを非常に苦々しく思いながらも、密かに、己の到着に伴うスペイン側の勝利を確信した。
間に合ってよかった、と、アレッチェは心底から思った。
クスコがインカ軍によって完全に陥落させられてからでは、せっかくの秘密兵器、「リマの褐色兵」を組織した意味もなくなる。
だが、この状況であれば、利用価値は十分にあった。
つまりは、同族であるインカ族を差し向けることで、トゥパク・アマルの攻撃の機先を封じようという作戦である。
本心ではスペイン渡来の白人の命を奪うことさえ躊躇があるに相違ないトゥパク・アマルにとって、同じインカ族の者たちを討つことなど極めて困難であろうことは、トゥパク・アマルという人物を知るアレッチェには、手に取るように読み抜けた。

果たして、そのアレッチェの推測は全く正しかったのだった。
アレッチェはすぐさまトゥパク・アマルらの本営のあるピチュ山指して、「リマの褐色兵」を差し向けた。
まさかのインカ族が討伐軍として向かってきたことで、トゥパク・アマルの軍勢は、大混乱に陥った。
アンドレスをはじめ、トゥパク・アマルの側近たちも、いかに敵の討伐側とはいえ、インカ族の兵たちをにわかには斬ることも、撃つこともできず、かくして、トゥパク・アマルも攻撃を指示することができなかった。
参謀オルティゴーサも血走った眼で顔を歪め、トゥパク・アマルの判断を仰いでくる。
「トゥパク・アマル様、いかにいたしましょう?!」
さすがのトゥパク・アマルも、この時ばかりは、これまでになく当惑と苦渋に満ちた表情である。
だが、毅然とした声で応える。
「ならぬ!!
彼らの命を奪ってはならぬ!!」
一方、「リマの褐色兵」たちは、同族であろうがなかろうが、躊躇することなくインカ軍に討ちかかってきた。
そのうえ、この機に乗じて、殆ど敗退していたはずのスペイン兵たちが息を吹き返したように再び攻撃を開始し、さらには、リマからの白人たちの援軍も怒涛のように討ちかかってきたのだった。
褐色兵に致命的な攻撃をしかけてはならぬ!!命を奪わずに、打倒せよ!――トゥパク・アマルの指令は、すぐに側近たちにも伝えられた。
しかしながら、不殺の攻撃――それは、あまりに困難な要求に違いなかった。
結果、インカ兵たちは、敵の刃を逃れながら、ひたすら防戦に回るしかなかった。
しかも、インカ兵が致死的な攻撃をしてこないと知った褐色の敵兵たちは、いっそう勢いづいて激しい攻撃をしかけてくる。
そのような激烈な状況の中、その逞しい大柄な肉体を俊敏に翻しながら、敵を殺さずに打ち倒すという極めて高度な技を展開しつつ敵中を走る、猛将ディエゴの姿があった。
実際、そのよう不殺の技を為し得る者など、インカ側にも数えるほどしかいなかった。
ディエゴは味方の士気を落とさぬよう、その鮮やかな腕を披露しつつ、「怯(ひる)むな!!今こそ、我らインカの底力を示そうぞ!!」と雄叫びを上げながら戦場を駆け抜け、味方の軍勢を激励して回っていた。
そんなディエゴだったが、不意に見てはいけないものを見てしまう。
一瞬、彼は目を疑った。
が、それが錯覚でないと知り、彼は急ぎそちらに駆け参じた。
狂気を孕んだ戦場の一隅の塹壕の中で、なんと、フランシスコが身を屈め、顔面蒼白のままに全身を痙攣させるように震えていたのだった。
その目の焦点も定まっていない。
「フランシスコ殿!!
な…何をしておられます?!
そのようなところにいらしては、かえって危険です!」
ディエゴが素早く塹壕に飛び降り、フランシスコを助けるようにその身を起こす。
「ディエゴ殿…!」
虚ろな、しかし、驚愕した眼でディエゴを見上げるフランシスコは、絶対に見られてはいけないものを見られてしまったとばかり、顔面をひくつかせながら、慄きの色をいっそう強める。
その額には無数の油汗が滲み出し、呼吸も非常に不規則になっている。
ディエゴの方もまた、驚きの眼差しで、蒼白なフランシスコの顔面を暫し呆然と見やっていたが、「とにかく、参りましょう!ここは危険です」と、フランシスコを抱えるようにして塹壕から慎重に飛び出すと、フランシスコを守りながら敵の刃をかわし、安全な場所を求めてさらに走った。
そのディエゴの腕の中で、フランシスコは全身にドッと油汗を噴出させながら、完璧に絶望的な目の色になっている。
(一番見られたくない側近に見られてしまった!!
このような恐るべき醜態を…――!!)
朦朧とした意識の中で、フランシスコは自分の体が暗黒の穴の中に落ちていくような感覚にとらわれていた。
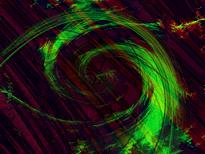
一方、トゥパク・アマルはその眼をわななくばかりに見開きながら、褐色の敵兵、あるいは白人の敵兵の無数の刃をかわしつつ、褐色兵の将を必死で探していた。
敵将を探しながら、同族にもかかわらず討ちかかってくる敵の褐色兵たちを鋭く観察する。
主に、斧や棍棒などの自弁の鈍器を手にして討ちかかってくる彼らは、決して、戦(いくさ)慣れしているようには見えなかった。
その身なりも貧しく、体格も惨めに痩せている者が多い。
風貌とて、戦士というより、明らかに貧しい農民に近いそれに見える。
恐らく、各地の貧困農民などが、金銭によって雇われて組織された傭兵(ようへい)の軍団ではないかと思われた。
トゥパク・アマル率いる戦慣れしたインカ軍が、多少なりとも本気でかかれば、あっさり撃退してしまえることは明白であった。
しかしながら、トゥパク・アマルには、本来はインカ族の貧しい農民たちであるに相違ない彼らに対して、いっそうのこと攻撃の刃を向けることは出来なかった。
(褐色兵の将はいずれに?!
果たして、これらの兵を率いている褐色兵の長はどの者か?!)
次々と討ちかかってくる討伐軍の刃をかいくぐりながら、褐色兵の将を探してトゥパク・アマルが疾走する。
何としても、褐色兵の敵将と話しをつけねばならぬ…――!!

今、褐色兵の将を探して敵中を疾走するトゥパク・アマルを、ビルカパサが必死で護衛する。
数々の褐色の敵に討ちかかられながらも、しかし、彼らを決して傷つけぬように細心の神経を払いつつ、トゥパク・アマルを敵の刃から守ってビルカパサも走った。
そして、トゥパク・アマルが「リマの褐色兵」の将を探しているのと同様に、褐色の敵将も、また、トゥパク・アマルを討ち取るべく血眼になって彼を探していた。
果たして、それらしき人物が、トゥパク・アマルの視界に飛び込む。
大柄な馬に跨り、毅然とした声音で褐色の傭兵たちを縦横無尽に指揮しているその男――それは、やはりインカ族の男であった。
艶やかな青銅色の肌に、筋肉質の立派な体格。
漆黒の巻き毛。
そして、非常に凛とした、極めて純粋にさえ見える、とても真っ直ぐな眼差しが印象的であった。
まだ30代前半と見える、生気溢れる若々しい風貌である。
しかし、反乱軍の将であるトゥパク・アマルを見つけたその男の目の中には、たちまち激しい憎悪の色が燃え上がった。
既に馬を降りているトゥパク・アマルは、己の足で4〜5メートルの近距離まで接近し、その馬上の人物を見上げた。
めったに感情を表に出さぬ彼であったが、今は、そのトゥパク・アマルの目に、明らかに必死の色が浮かんでいる。
何としても、この褐色の敵将と話しをつけねばならぬ!!彼の言い分を聴き、説得せねばならぬ!!金で雇われた貧困農民たちであれ、スペインの役人から戦うことを強要された者たちであれ、インカ族同士で殺戮し合うなぞ、このような言語を絶する馬鹿げた茶番を一刻もはやく終わらせるために…――と、その目は激しく訴えていた。
「そなた、なぜ…――!」
トゥパク・アマルが言葉を発しかける。
が、その褐色の敵将は、「話すことは何も無い!!」と、トゥパク・アマルの言葉を鋭く遮り、馬上から憎々しげにトゥパク・アマルを睨みつけた。
そして、次の瞬間、その褐色の敵将は、いきなり鋭利な半月刀を振り上げると、そのままトゥパク・アマルの急所めがけて切りかかってきた。
さすがにトゥパク・アマルは俊敏な身のこなしで刃をよけたが、それでも、左肩から腕にかけて、その異様に鋭利な刃物に切り裂かれ、ザックリと皮膚が開いて血がほとばしった。
「トゥパク様!!」
すかさずビルカパサが生ける盾のごとくに、褐色の敵将とトゥパク・アマルの間に割って入る。
しかし、敵将は馬上から振りかぶるがごとくの勢いで、再び必殺の刃を振り下ろす。
ビルカパサが目にもとまらぬ俊敏さで、己の剣によってそれを宙空で防いだ。
それと共に、ビルカパサの、その野性的な眼光が非常に険しく光った。
トゥパク・アマルが間髪入れず、「ビルカパサ!!討ってはならぬ!!」と、その腕から大量の血を滴らせながら鋭い声で、今にも切りかからぬばかりのビルカパサを制する。
その隙に、褐色の敵将が、さらなる刃を振り下ろさんとする。
そこへ、疾風のごとくに飛び込んできたアンドレスが、己の重厚なサーベルで敵の半月刀をガッチリと押さえ込んだ。
その瞬間、剣と刀とがぶつかり合う、まさしく天にも届くがごとくの鋭い金属音が周囲に響き渡った。
アンドレスは剣で相手の刀を抑えたまま、「ビルカパサ殿!はやくトゥパク・アマル様を安全なところへ!!」と鋭い声で言い放つ。
「アンドレス様、かたじけない!!」と、ビルカパサは、そのままトゥパク・アマルを抱え込むようにして、次々と襲い来る敵兵たちをかわしながら走り去った。
アンドレスも褐色の敵将と刃を交えながらも、しかし、決して敵将を傷つけぬよう細心の注意を払う。
さすがのアンドレスの額からも、幾筋もの汗が頬を伝って流れ落ちた。
そして、彼もまた、敵将の意識が去り行くトゥパク・アマルの方に移った一瞬の隙に、素早く雑踏の中に姿を消した。

トゥパク・アマルが褐色兵を攻撃しないことに勢いを得たスペイン側は、アレッチェの指示によって、全く言語道断なことだが、男女を問わずクスコ市内のインカ族の人々を拉致し、縛り上げ、なんと、彼らを生ける盾としたのである。
スペイン兵たちは縛り上げたインカ族の人々の後ろに身を隠し、インカ兵たちを撃ちまくった。
言うまでもなく、トゥパク・アマル率いるインカ軍が、生ける盾とされた兄弟姉妹を殺してまで、スペイン軍に攻撃を続けることなどできようはずがない。
かくして、トゥパク・アマルの指示によって、同族の褐色兵への致命的な攻撃を止められたままに敵に討たれ、あるいは、恐怖の極みから反射的に同族にさえ反撃を抑えられずにいる自軍の兵を前にして、しかも、ついには生ける盾とまでされたインカ族の人々の命を守るため、トゥパク・アマルは退却の号令をかけざるをえなかった。
これ以上、味方にも「敵」にも、もはや犠牲を増やすことはできなかったのだ。
彼の指揮のもと、やむなくインカ軍はピチュ山を放棄し、後方の山岳地帯へと退いた。
かくして、インカ軍は、牙城クスコ奪還を目前にして、無念の敗退を余儀なくされたのであった。
 インカ軍の敗走する姿に、モスコーソ司祭や巡察官アレッチェがどれほどに満悦気な表情を浮かべていたかは、もはや言うまでもない。
インカ軍の敗走する姿に、モスコーソ司祭や巡察官アレッチェがどれほどに満悦気な表情を浮かべていたかは、もはや言うまでもない。
モスコーソはアレッチェの組織した「リマの褐色兵」をいたく気に入り、既に、この時点で、完全なる勝利を確信したほどであった。
モスコーソは、ひどく気に入った、その褐色兵の将に会うことを所望していた。
アレッチェは、褐色の討伐隊の将を執務室に呼んだ。
まもなく、逞しくも、非常に真っ直ぐな澄んだ目をしたインカ族の男が現われる。
その褐色の男は、この国最高の司祭モスコーソを前にして、すかさず跪いて深々と礼を払った。
モスコーソはえらく満足そうにキュッと目を細め、己の前に傅(かしず)いている凛々しい青銅色のインカ族の男に「うむ、うむ」と幾度も頷いた。
「そちの働き、実に見事であった。
余はいたく感動したぞ」
そのモスコーソの言葉に、褐色兵はまだ頭を深く垂れたまま、「身に余る御言葉、モスコーソ司祭様の御為であれば、この命惜しくはございませぬ」と、深い感動を滲ませた声で応える。
モスコーソの満悦顔が、この上なくなったのは言うまでもない。
「インディオの中には、トゥパク・アマルのような悪魔のごとくの反逆者もいるかと思えば、そちのような、実に忠良なる臣民もいるのじゃな!インディオもまだ捨てたものではないらしい」としみじみと語りながらも、モスコーソの中に、この眼前に傅く男がトゥパク・アマルだったら…――という密かな願望を伴った妄想がよぎっていく。
一方、「身に余るお言葉、真に、わたくしにとりまして最上の日でございます」と、未だ深く礼を払っているその褐色兵に、「そちの名は何と言う。顔を上げておくれ」と、あの舐めるような視線になってモスコーソが言う。
司祭の言葉にすっかり恐縮している褐色兵に向かって、二人の様子を伺っていたアレッチェが「構わぬ。顔を上げて、おまえの名を告げよ」と、淡々とした声で言う。
モスコーソも、あの瞳の見えぬほどに細めた目で、唇の端を不自然に吊り上げながらじっと褐色兵に絡みつくような視線を投げていた。
褐色兵は、やや躊躇(ためら)いがちに、ゆっくりと顔を上げる。
漆黒の巻き毛に縁取られた逞しくも端正な風貌に、やはり、あの純粋で真っ直ぐな瞳が非常に印象的な精彩を放っている。
モスコーソは、たいそう満足そうに目をキュッと細めたまま、幾度も頷いた。
「そなたは勇ましくも、まるで褐色の天使のごとくに澄み切った目をしておる。
名は何と申すか」
「フィゲロアと申します」と、深く礼を込めた、感動と興奮からやや上擦った声で恭しく応える。
すると、「フィゲロア殿…!!」と、あの駆け寄るがごとくの仕草で、モスコーソは跪いている褐色兵の前に自らも跪き、己の両腕で褐色兵の両肩を抱きかかえるような格好をした。
傍から見ているアレッチェは、そのモスコーソの態度のあまりに大袈裟で白々しい様子に、心の底で冷笑せずにはいられない。
しかしながら、当のフィゲロアは、モスコーソのその様子に深い驚きと感動を隠せぬ様子で、澄んだ瞳を大いに輝かせていた。
「フィゲロア殿、忠良なる神の御前の子羊よ、本当にそなただけが頼りじゃ。
この国の神聖なるキリスト教を悉く血と火で汚すあの謀反人から、この国を、そして、このか弱き牧者を守っておくれ」
すがるような眼で弱々しい声を発するモスコーソに、フィゲロアは庇護するような頼もしい眼差しを向ける。
それから、深い誠意を込めた声で「この命のすべてを懸けて、司祭様を、そして、この国のキリスト教と平穏な秩序をお守りいたします」と、誓詞を立てるがごとくに応えた。
すっかりご満悦も極まった様子でモスコーソが立ち去ると、改めて、アレッチェがフィゲロアに向き直った。
「確かに、おまえの働き、見事であった」
アレッチェの言葉に、フィゲロアは再び恭しく礼を払った。
「だが、トゥパク・アマルを目前にしながら仕留められなかったとは、極めて残念だ」と、ひどく冷ややかな声でアレッチェが言う。
そのアレッチェの言葉に、「申し訳ございませぬ」と低く応えるフィゲロアの握り締めた拳は、悔恨のためであろう、わななくように震えだす。
「トゥパク・アマルを殺さず、生け捕りにするのだ。
反乱を完全に鎮圧するために、聞き出さねばならぬことが山ほどある」
「はい」と答えるフィゲロアの瞳に、憎悪を秘めた、激しい闘争的な炎が燃え上がった。
アレッチェは満足そうにその瞳の色を見ながら、「トゥパク・アマルに思うようにさせてはならぬ。あの男は、再び『インカ皇帝』として君臨し、独裁政治を敷こうとしている。おまえがそれを防ぐのだ」と、いかにも緊迫した声で言う。
フィゲロアは「よく心得ております」と、毅然とした声で応える。
アレッチェも頷き返し、それから、「下がって休め」とその褐色兵を退室させた。
一人執務室に残ったアレッチェは、既に夕闇に包まれつつある窓外に目を向けた。

この牙城クスコを、反乱軍から守り切れたことには、やはり深い安堵があった。
そして、「リマの褐色兵」が、予想以上に効果的であったことにも満足を覚えていた。
軍団の将、フィゲロアは、インカ族ではあるものの、首府リマというスペイン的気風の強い環境で生まれ育ち、裕福で進歩的な考え方を持つ貿易商の両親のもとで、幼少時から西洋的な教育を授けられて生育してきた。
彼の家系がインカ皇族ではなかったことも、彼を過去のインカ帝国への執着から解放するのを容易にした。
開国に積極的且つ進歩的なフィゲロアの父親はスペイン人に協力的であり、結果として、スペイン人役人からの覚えもめでたく、その生活は優遇されたものだった。
また、彼の両親は敬虔なカトリック教徒でもあり、この国最高の司祭であるモスコーソを深く信奉してもいた。
彼及び、彼の家族は、スペイン侵略後の新しい時代の中を巧みに泳いでくることができた極少数のインカ族の部類に属する者だったと言えるだろう。
そのようなフィゲロアにとって、現在の植民地政策は、必ずしも否定されるべきものとは映っていなかった。
西洋的な思想や文化から学ぶことの実に多いことも知っていた。
「暴政」と見える部分は、より進歩的で成熟した文化や政治を受け入れていく過渡期の、やむを得ぬ必要悪として認識してもいた。
そんなことよりも、今更『インカ皇帝』なるものの出現によって、彼から見れば、実に原始的で土着的な世界へ、しかも、独裁的な治世へと後戻りすることの方が、はるかに危惧されることであった。
そうしたフィゲロアの考え方は、スペイン側にとっては非常に都合のよいものであった。
しかも、フィゲロア自身の特性としてのその純粋性は、ある意味では、洗脳のされやすさでもあったのだ。
アレッチェが彼に目をつけ、利用価値を見出したのも、必然のことであったろう。
この不安定な植民地下で、こうした反乱の起こる可能性を十分に予測していたアレッチェは、フィゲロアのような環境のインカ族の子弟たちに秘密裏に軍事訓練を施してきた。
そして、その者たちの中でも、特に統率力と武勇に秀でていたのがこのフィゲロアだった。
結果、此度の将として白羽の矢を立てられるに至ったが、まさしくフィゲロアにとってもこのクスコ戦は、後に明らかになるように、アレッチェに目をつけられた時から宿命づけられていた彼自身の悲愴な運命のはじまりでもあったのだ。

なお、フィゲロアの元にインカ族の傭兵を組織するに当たって、アレッチェは強引にリマ界隈の貧困農民たちを参戦させたが、同族に刃を向けるという彼らの抵抗感を割り切らせるために、単に一定の報酬を保障するに留まらず、トゥパク・アマルの首に莫大な報奨金をかけていた。
トゥパク・アマルを生け捕りにした者には、なんと2万ペソもの大金を与えると、全軍の兵に、そして、国中に、広く確約し布告していた。
当時のその額は邦貨にすれば実に1千万円にも相当し、当時としては、それだけの金額があれば一生贅沢に暮らせるばかりか、子や孫の代までの生活を保障し得るほどの目を見張るような大金であった。
日々の一切れのパンにさえ苦心惨憺たる思いで生活をしていた極貧のインカ族の農民たちにとって、その金額は、その目を眩(くら)ませるに十分だったのだ。
このように、同族同士で斬り合いをさせるためには、それなりのコストをかける必要があることをアレッチェはよく認識していた。
そして、逆に、それだけ捻出すれば、同族同士でさえ殺し合うのだと…――所詮、人間などそのようなものなのだ、と、アレッチェは皮相な冷笑を浮かべながら、既に日の落ちた窓外の暗闇にじっと視線を投げた。


